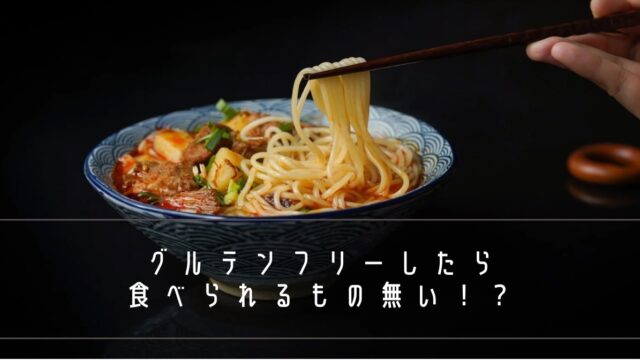「寝不足で頭が回らない」「昼間ぼーっとして集中できない」 そんな経験、誰にでもあると思います。
堺市堺区の「たかおか鍼灸整骨院」院長のりょうすけです。
実は、当院へ腰痛や肩こりで来院される方の多くが、同時に「睡眠不足」や「寝つきの悪さ」を抱えています。
実は、睡眠不足は単に“眠い”だけでなく、心と体のあらゆる働き、そして「痛みの回復」に大きな悪影響を与えることがわかっています。
この記事では、鍼灸整骨院の現場で感じる実例とともに、睡眠の仕組みをホルモンの観点からわかりやすく解説します。
睡眠は「ホルモンのリズム」でつくられる
眠気をつくるホルモンとして有名なのが「メラトニン」です。
夜になるとメラトニンが分泌され、体温を下げ、心拍数を落とし、「そろそろ眠る時間だよ」と体に合図を送ります。
このメラトニンは突然できるわけではありません。
その“原料”となるのが「セロトニン」というホルモンで、さらにセロトニンの材料はタンパク質に含まれる「トリプトファン」というアミノ酸です。
つまり── 「朝にセロトニンを作り、夜にメラトニンへ変化させる」 という流れが、質の良い睡眠、そして痛みのない体を作る鍵になります。
朝の光と朝食が「夜の眠り」を決める
メラトニンの材料であるセロトニンは、朝の太陽光を浴びることで活性化します。
また、材料となる「トリプトファン」を食事から摂ることが必要です。
【トリプトファンを多く含む食材】
- 卵(特に黄身)
- 納豆・豆腐などの大豆製品
- 魚(カツオ・マグロなど)
- 鶏むね肉
- チーズ・ヨーグルト
これらを朝食に取り入れ、朝日を浴びることで、夜には自然にメラトニンが分泌されやすくなり、眠りのリズムが整います。
🌞 朝に「光+タンパク質」をしっかり取ることが、夜の“深い眠り”と、翌朝の「腰の軽さ」につながります。
睡眠不足がもたらす3つの悪影響
① 集中力・感情のコントロールが低下
脳の「前頭前野」がうまく働かず、注意力・判断力・感情の安定が乱れやすくなります。
イライラしやすい、ミスが増えるなどは典型的なサインです。
② 自律神経が乱れ、腰痛が慢性化する
寝不足は交感神経(活動モード)を過剰に刺激し、リラックスを担う副交感神経の働きを妨げます。
結果として、筋肉が緊張し続け、肩こり・腰痛・頭痛などが起こりやすくなります。
③ 免疫力と修復力の低下
睡眠中に働く免疫細胞の活性が低下し、疲労が抜けにくくなります。
臨床の現場で感じる「睡眠と回復の差」
当院でも、同じような施術をしていても「よく眠れている人」と「寝不足の人」では回復のスピードに明確な差が出ます。
睡眠がしっかり取れている方は、痛みの改善が早く、再発も少ない傾向があります。
つまり、良い睡眠は「施術の効果を最大限に引き出す土台」と言えるのです。
私の体験談:睡眠リズムを整えて気づいたこと
以前の私は夜更かしが多く、翌朝の頭の重さや集中力の低下に悩まされていました。
さらに、家でもイライラして家族との空気がピリピリ…(妻の機嫌も最悪に💦)
そこで、22時〜23時に就寝し、朝5〜6時に起床するように習慣を変えたところ、朝から頭がスッキリし、仕事の集中力も上がり、家庭も平和になりました。
まさに「良い睡眠は心の余裕」だと実感しています。
睡眠の質を上げるための5つのポイント
- 22時〜2時の間に眠る(細胞が修復されるゴールデンタイム)
- 朝に日光を浴びる+タンパク質を摂る
- 寝る直前のスマホ・テレビを控える(ブルーライトは脳を覚醒させます)
- ぬるめのお風呂でリラックス
- カフェイン・アルコールを控える
まとめ:睡眠は最高の治療
質の高い睡眠こそ、最高のセルフケアです。
もし「寝ても疲れが取れない」「朝起きた時に腰が痛い」と感じる方は、体の歪みや自律神経の乱れが原因かもしれません。
堺市堺区の「たかおか鍼灸整骨院」では、鍼灸や整体で自律神経を整えることで、メラトニンの分泌を安定させ、“自然に眠れる体”へと導くサポートをしています。
一人で悩まず、ぜひ一度ご相談ください!